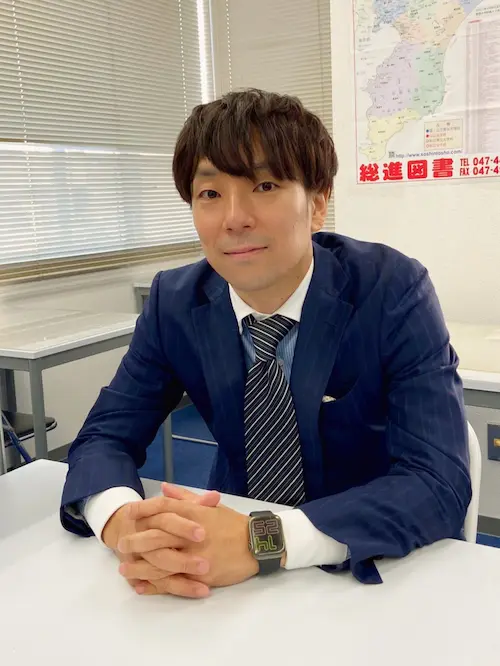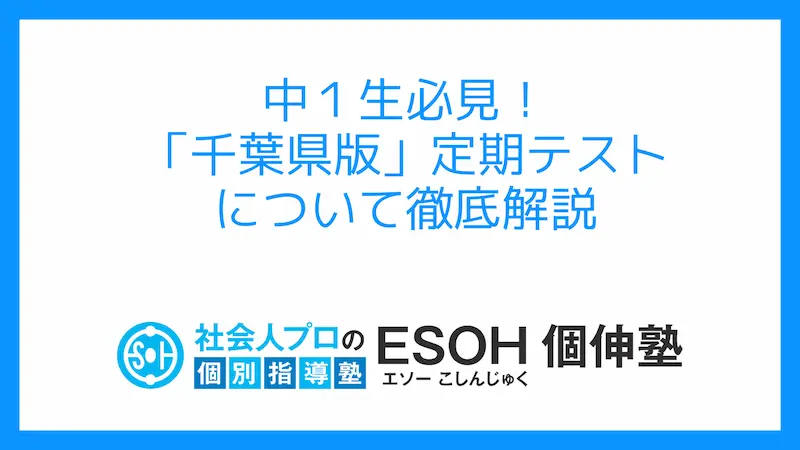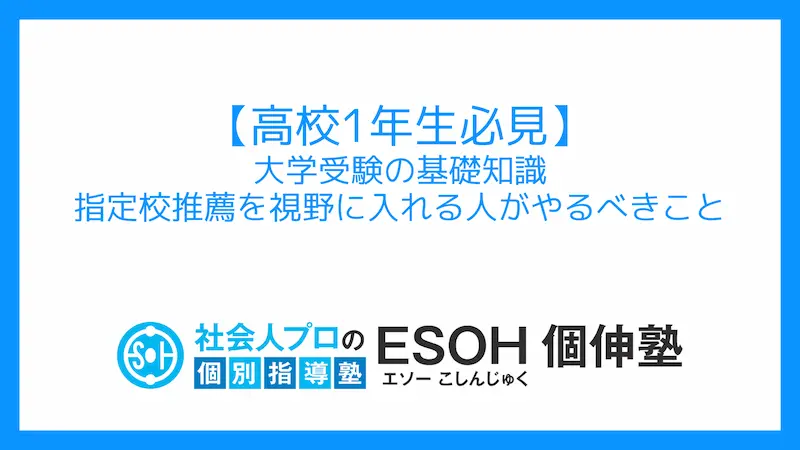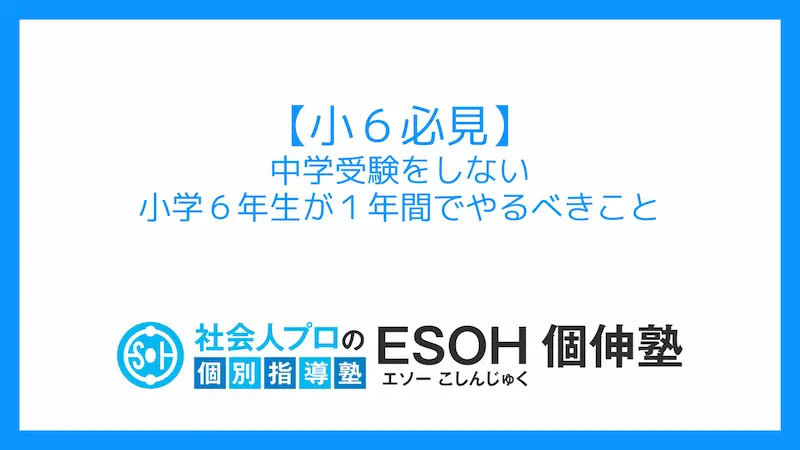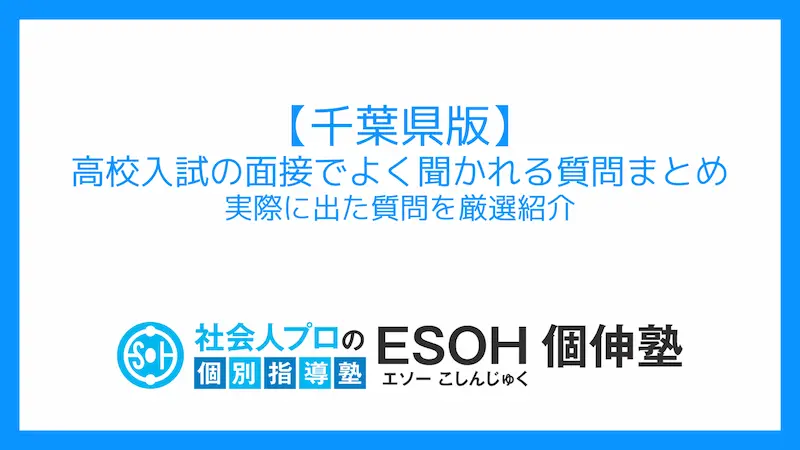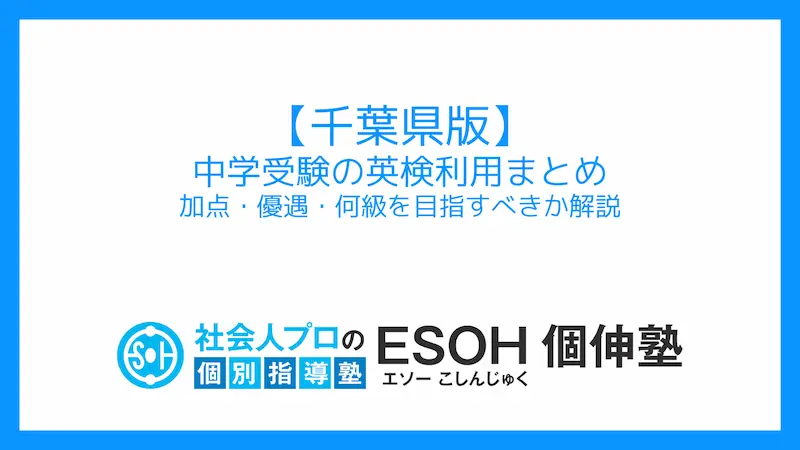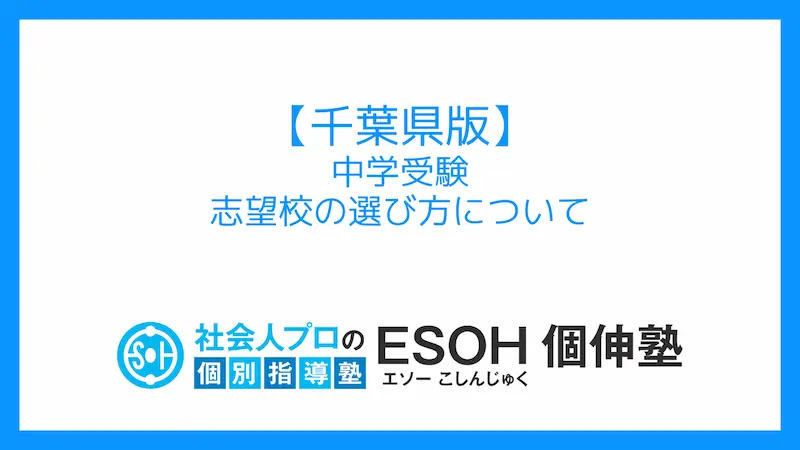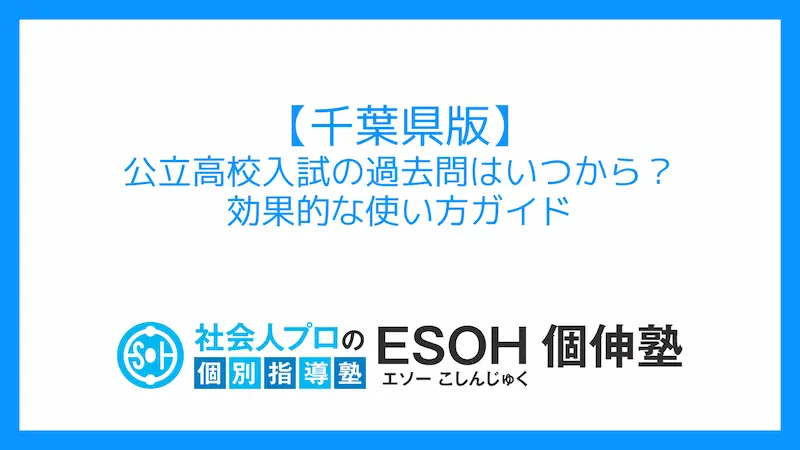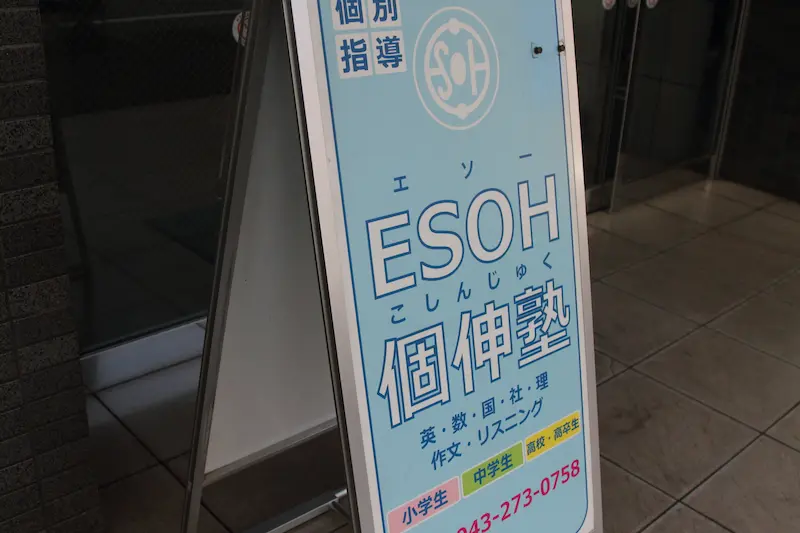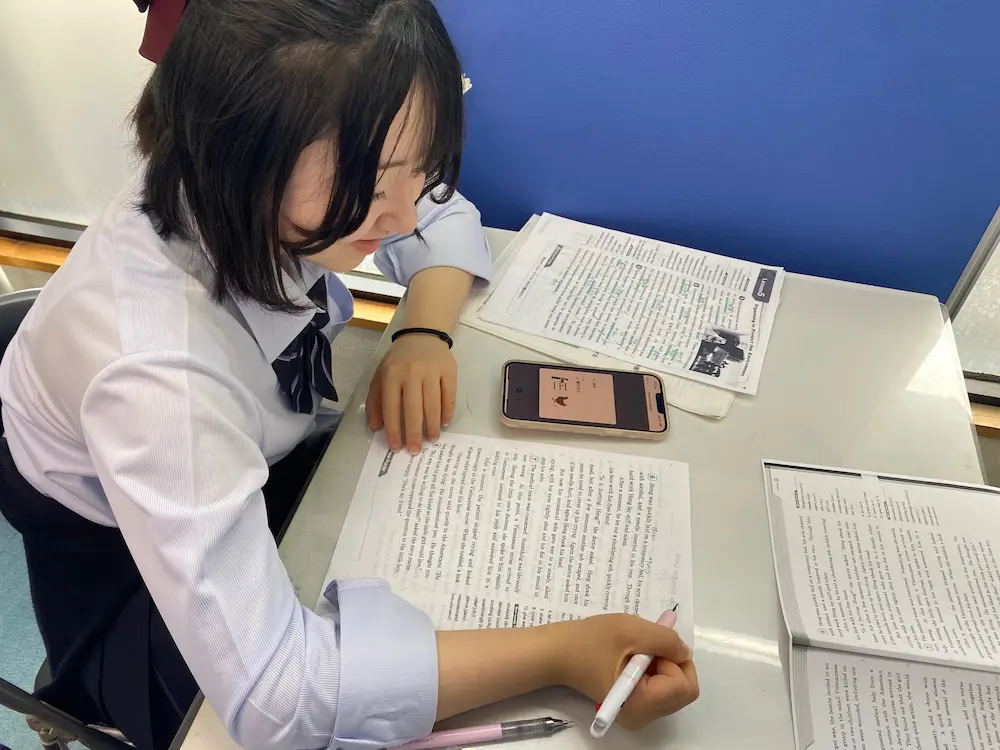春になりました。中学に入学した生徒、保護者のみなさまご入学おめでとうございます。
中学に入ると、部活動に入ったり、学校の時間割が変わったりなど、小学校の時と生活が大きく変わります。
そして、中学に入ると『定期テスト』が行われます。
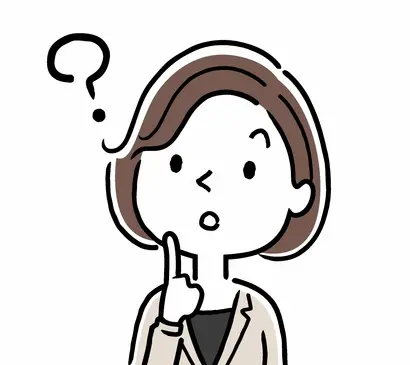
定期テストは内申点に関わるって聞いたけど、どのようにかかわってくるの?
どんな対策をしたら良いか、不安ですよね。
そこで今日は、中学から始まる『定期テスト』についてまとめてみたいと思います。
定期テストはなぜ大切なのか?についてしっかりと解説をしていきたいと思います。
この記事を読むべき人
・中学1年生のお子様をお持ちの保護者様
・定期テストの基本的な内容について把握をしたい人
・定期テストの勉強方法について知りたい人
自己紹介
【自己紹介】
エソー個伸塾 塾長 原田健司
千葉県で社会人プロの個別指導塾「エソー個伸塾」を4教室展開。エソー個伸塾には約40名以上の講師が在籍しており、講師の平均指導歴は10年以上。指導力の高さには自信があります。1人1人の目標に合わせた個別指導を行っています。
では、早速解説していきます!
定期テストとは
定期テストとは、中学や高校などで年に4~5回実施されるテストで、教科ごとの学習の到達度を確認するテストです。授業で学習した内容がきちんと理解が出来ているかを評価します。
テストの成績は通知表の評定に反映されるため、中学生にとって非常に重要なテストです。
定期テストの種類と教科
定期テストには「中間テスト」と「期末テスト」があります。
【中間テスト】
学期の中ごろに行われる。
国語・数学・理科・社会・英語の5教科のテストが実施されます
【期末テスト】
学期の終わりごろに行われる。
国語・数学・理科・社会・英語の5教科に加えて音楽・美術・保健体育・技術家庭の4教科が実施されます。
特に期末テストは教科も多く、範囲も広くなることが多いためしっかりと学習計画を立てて臨むことが大切です。
定期テストの年間スケジュール
定期テストの時期については以下の表のようになっています。
定期テストは3学期制の学校では1学期、2学期の中間テストと期末試験、3学期の期末試験の年5回、前後期制の学校では前期中間、前期期末、後期中間、後期期末の年4回実施されます。
【3学期制の学校の年間定期テストスケジュール】
| 学期 | テスト | 時期 |
| 1学期 | 1学期中間テスト | 5月中旬から下旬 |
| 1学期期末テスト | 6月下旬から7月上旬 | |
| 2学期 | 2学期中間テスト | 10月中旬から中旬 |
| 2学期期末テスト | 11月下旬から12月中旬 | |
| 3学期 | 3学期期末テスト | 2月下旬から3月上旬 |
【前後期制の定期テスト年間スケジュール】
| 学期 | テスト | 時期 |
| 前期 | 前期中間テスト | 6月上旬頃 |
| 前期期末テスト | 8月末から9月上旬 | |
| 後期 | 後期中間テスト | 中3だけ11月上旬に行うとこ 11月下旬から12月上旬 |
| 後期期末テスト | 中3なしのところ 2月中旬 |
小学校と中学校の授業やテストの違いについて
定期テストを理解するには、小学校と中学校の学習の違いを理解することが大切です。
小学校と中学校では、授業やテストの違いについて理解しましょう。
1.教科ごとに先生が違う
小学校では、多くの場合1人の先生がほとんどの教科を教えています。しかし、中学では教科ごとに先生が異なり、教え方や課題の出し方などが異なります。そのため、生徒側としては、その先生のスタイルに合わせて学習を進めていく必要があります。
2.授業の進みがはやい
中学の勉強は、小学校に比べて分量が多いため、進むスピードが速いと感じる生徒も多いと思います。また、部活動に入った生徒など、帰宅する時間が今までよりも遅くなることも多く、より学習時間を確保するのが難しくなる場合があります
3.テストが違う
小学校のテストはカラーテスト呼ばれるカラーの両面のテストが主なテストで、その単元が終わるごとに実施されることが多いです。
中学では、今回のメインのテーマである定期テストと実力テストがあります。テストの範囲が小学校で実施されるカラーテストに比べて範囲が広くなり、しっかりと復習して定着をさせておかないと高得点を取るのが難しいです。
まとめ
上記のように、小学校と中学校では授業やテストなど学習に関する環境が大きく変わります。
私は、「生活スタイルが変わるタイミングでその都度学習のスタイルをセットする」ことが大切だと考えています。
中学に入学するタイミングや、中3になって受験勉強に本腰を入れようなど、自分の生活が大きく変わるタイミングで客観的に自分のスケジュールを見直します。そうすることで、必要なことをやる時間をどのタイミングでやるのかを決めて捻出することができます。
是非、新しい生活のリズムを整えてみて下さい。
定期テストの平均点は60点
定期テストの話に戻りましょう。
定期テストは、だいたい平均点が60点くらいになるように基本問題と応用問題のバランスを考えて作られます。
ただ、そのテストによって教科ごとに平均点が50点台になったり、70点台になったりすることがあります。
テストの平均点が70点なら易しかったと言え、平均点が50点以下だとすると、テストが難しく、応用が多かったということが言えます。平均点に対して自分がどの程度得点できたのかを把握していくことで自分の目標が定まっていきます。
ただし、中学1年生の最初のテストは平均点が高くなる傾向があるのでしっかりと基礎固めをしましょう。
千葉の公立高校の入試は中1最初の定期テストから内申点に直結する
ここでは定期テストはなぜ大切なのか?について解説します。
定期テストは全国で実施され、全国どの地域では内申点として使われるのですが、実は地域によってどの時期の成績が内申点として使われるかというが異なります。
そして、ここが千葉県の公立高校入試を語るうえでポイントとなってくるのですが、千葉県の公立高校の入試では、中1から中3までの通知表の成績がすべて内申点として使われます。
つまり、定期テストの得点は中学1年生の時期からその教科の成績に直結し、高校受験の合否にも影響してくる大切なものです。
塾で小学6年生の保護者と話していると

「え!そうなんですか?中1の最初くらいは当たって砕けろで良いと思っていました!」
とおっしゃる保護者様もいらっしゃいますが、ここは注意が必要です。
内申点の決まり方や、千葉県の公立高校の入試制度について詳しく書いた記事もありますのでよろしければそちらもあわせてご覧下さい。
【最新版】千葉県の高校入試は内申点が大切!その理由と計算方法を解説
評定をよくするために気を付けること
通知表の評定を要するためにどのようなことに気を付けて行けばよいかについて説明します。
その1.定期テストで良い点数を取る
定期テストは通知表の評価に最も大きく直結します。毎回の定期テストに向けてコツコツ学習する習慣をつけることが定期テストで良い得点を取るコツです。3週間前から準備を始め2週間目くらいから本格的に対策が出来るように計画的に学習を進めましょう。
その2.課題の期限を守ってしっかりと提出をする
課題提出も評定に入ります。中学では、テストの当日にテスト範囲までのワークをやって、答え合わせをして提出というような課題が良く出ます。提出物は「どのように勉強に向き合っているか」が伝わります。答え合わせについても、ただ〇と×をつけるだけでなく、どこで間違えたのか、答えに至る道筋を書き込むなど、丁寧に取り組むことで先生の見方も変わります。
コツコツと丁寧に取り組みましょう。
その3.授業にも積極的に参加をする
授業の態度などについても評定に入ります。授業中に手を挙げ、発表することでしっかりと授業に参加していることをアピールできます。
でも「授業中に手を挙げるのってちょっと勇気がいる・・・」という子もいますよね。
そんな子でもうなづいたり、先生の顔をしっかりと見て授業を受けたり、ノートをしっかり取るなども立派な参加です。自分なりの関わり方でしっかりと授業に参加しましょう!
エソー個伸塾の定期テスト対策
エソー個伸塾では、生徒の中学校、目標に合わせて個別指導をしています。
- 社会人プロ講師が1人1人の目標に合わせて個別に指導
- 通常の授業で通っている中学の教科書に合わせた定期テスト対策が行える
- 千葉県で13年以上の実績!地域の学習状況を熟知
社会人プロ講師が1人1人の目標に合わせて個別に指導
エソー個伸塾は社会人プロ専門の個別指導塾です。全ての授業を社会人のプロ講師が責任をもって1人1人個別指導します。
通常の授業で通っている中学の教科書に合わせた定期テスト対策が行える
千葉県の公立高校入試では内申点が非常に重要です。そのため、授業や保護者面などを通じて内申点の重要性をお伝えしています。また、普段の授業で学校の教科書にぴったり合ったテキストを使って定期テスト対策を中心に授業を行うこともできます。自分の目標点数にあった授業を行っています。
千葉県で13年以上の実績!千葉県の地域の学習状況を熟知
エソー個伸塾は千葉県で開校して今年で12年になります。開校当初から社会人プロ講師にこだわり質の高い授業にこだわってきました。千葉県公立高校指導実績が非常に多く、千葉県の公立高校特有の問題もしっかりと対応します。